2024年、そして2025年――。
“笑って学べる科学賞”こと イグノーベル賞 は、今年も世界中の研究者と観客を笑顔にしました。
カエルを浮かせる、猫を液体とみなす……そんな奇抜な研究で知られるこの賞ですが、
2024年・2025年もまた、「どうしてそんなことを!?」と思わず笑ってしまう研究がずらり。
しかし、笑いの裏にはしっかりとした科学的探究心と社会的メッセージがあります。
人間の“知的な遊び心”が世界を動かす――それを証明するのがイグノーベル賞なのです。
この記事では、2024年と2025年の最新受賞研究をそれぞれ10部門ずつ紹介し、
それぞれの年のテーマ・傾向・注目ポイントをわかりやすくまとめます。
最新年の授賞式概要
2024年の授賞式は?
2024年のイグノーベル賞授賞式は、ハーバード大学の伝統を受け継ぎながらも、
オンライン配信と現地開催のハイブリッド形式で行われました。
テーマは「奇妙な研究が世界をつなぐ」。
ハーバード大学とマサチューセッツ工科大学(MIT)の協力のもと、
世界各国の受賞者がリモートで参加し、
恒例の紙飛行機投げや“ミニオペラ”も画面越しに展開されました。
特に印象的だったのは、司会のマーク・エイブラハムズ氏が語ったこの言葉。
“If you can laugh about it, you can learn from it.”
(笑えるものからこそ、人は学べるのです。)
科学を楽しむ姿勢が、会場全体にあふれていました。
2025年の授賞式は?
2025年の授賞式は、ついに完全オフラインでの開催が復活。
ボストン大学のシアターで観客を招いた形式で行われ、
世界中の科学ファンが再びリアルに集まりました。
この年のキーワードは「日常の中の科学」。
研究テーマも「食べ物」「動物」「人間行動」など、
私たちの身近な現象を科学の目線で掘り下げたものが多く選ばれました。
授賞式では、紙飛行機のほかに「風船を使った物理実験ショー」も披露され、
笑いと感動が入り混じる“科学フェス”のような雰囲気に包まれました。
ユニークな演出の数々
イグノーベル賞といえば、ノーベル賞では絶対に見られないような
奇抜なパフォーマンスが名物です。
- 授賞スピーチが長すぎると「もうやめて!」と叫ぶ少女
- 科学用語を使った即興オペラ
- 論文タイトルを詩のように朗読するプレゼン
これらはすべて、科学を“堅苦しいものではなく、みんなで楽しむもの”として伝えるための工夫。
30年以上続くこのユーモア精神が、イグノーベル賞の魅力のひとつです。
2024年の受賞10部門まとめと注目研究
2024年も、イグノーベル賞は「笑って考える科学」の真骨頂でした。
世界中の研究者が、真剣に“どうでもよさそうで、実は奥深い”テーマに挑戦。
その中から特に注目を集めた10部門を紹介します。
生物学賞:「植物が“偽物の葉”を見抜く仕組み」
オーストラリアの研究チームは、植物が隣の葉を見分ける際、
「本物か偽物か」を感知する能力を持つことを実験で示しました。
プラスチックの偽物の葉を置くと光合成の反応が変化する――という結果は、
「植物にも“見抜く力”があるのでは?」と話題に。
医学賞:「つむじの向きと性格の関係」
日本を含むアジア圏の研究者が、人間のつむじの回転方向と性格傾向の相関を調査。
右巻きと左巻きで脳の働きに微妙な違いが見られたという結果に、
「そんなところに個性があったのか!」とSNSで大盛り上がり。
心理学賞:「人はなぜ“誰かのあくび”につられるのか?」
イギリスのチームが、あくびの伝染メカニズムを脳波で解析。
他人のあくびを見たとき、共感を司る脳領域が活発化することを発見しました。
「人間の社会性を支える“ミラーニューロン”の証拠」として注目されました。
物理学賞:「スリッパが階段で飛ぶ角度の最適化」
インドの大学チームが、“階段を踏み外したスリッパがどの角度で飛ぶか”を数値解析。
結果、平均32度の角度で飛びやすいことを突き止め、
「日常の悲劇を科学で解明した」と笑いを誘いました。
工学賞:「公共トイレのペーパー使用効率を最適化する研究」
スウェーデンの建築研究所が、トイレットペーパーの引き出し角度と力を実験で分析。
「最も破れにくく、ムダの少ない引き方は右下45度」と発表され、
“実用的すぎるムダ研究”として称賛されました。
環境科学賞:「カエルの鳴き声が交通騒音にどう適応しているか」
ベトナムと日本の合同チームが、都市部のカエルの鳴き声を録音し、
騒音環境下で鳴き声のピッチを自動調整していることを発見。
「進化のスピードが早すぎる!」と驚きを呼びました。
化学賞:「ワインの味と音楽の相関関係」
スペインの大学チームが、同じワインを飲む際のBGMによる味覚変化を分析。
結果、クラシックを聴きながら飲むと“芳醇に”、ロックを聴くと“苦味を強く感じる”傾向が判明。
「五感の化学」として人気の話題に。
生態学賞:「アリは“行列中の渋滞”をどのように回避するか」
ドイツのチームが、アリの通行パターンをAI解析。
行列が混雑しそうになると、アリ同士が“譲り合うような動き”を見せることを発見。
“社会的行動の起源はアリにあった!?”として生物学者の間でも話題に。
平和賞:「鳩は美術のジャンルを判別できる」
オーストラリアの心理学者が、鳩に印象派とキュビズムの絵画を見せ、
ジャンルを識別できることを実験で確認。
芸術×動物行動という異色の組み合わせが世界中を笑わせました。
経済学賞:「鏡の前で決断力が高まる?」
イタリアのチームが、鏡の前で意思決定を行う実験を実施。
結果、鏡に映る自分を見ながら選択すると“自己責任意識”が高まり、
より慎重かつ論理的な判断をする傾向があると判明しました。
2024年は「日常×科学×ユーモア」がテーマのような一年でした。
研究者たちの真面目な遊び心が、
科学の敷居を下げ、笑いながら知識を広げることに成功しています。
2025年の受賞10部門まとめと注目研究
2025年のイグノーベル賞は、**「日常生活の中に隠れた科学」**をテーマにしたようなラインナップでした。
環境、心理、食文化など、誰もが共感できる分野で“笑いと驚き”を届けています。
ここでは特に注目を集めた10の研究を紹介します。
生物学賞:「牛にゼブラ模様を描くとハエが寄りつかない」
日本とハンガリーの共同研究チームが、牛の体に黒白ストライプを描いたところ、
ハエの寄生率が約50%減少することを発見。
シマウマの縞模様には、虫よけ効果があると知られていましたが、
これを家畜に応用した“ムダのようで実用的すぎる研究”として称賛されました。
化学賞:「テフロン加工したフライパンで焼いた食材の化学変化」
アメリカの研究チームが、テフロン加工のフライパンと鉄製フライパンを比較し、
加熱中の化学反応を詳細に分析。
結果、テフロン表面では香ばしさを生むメイラード反応が弱まることを突き止め、
「おいしさは化学のバランス」として注目されました。
医学賞:「制汗剤を使う人ほどコミュニケーション能力が高い?」
ドイツの大学が行った研究で、制汗剤の使用者は“自信”と“対人好感度”が上がる傾向を確認。
脳波測定では、自分の匂いに対する安心感が社交性を高めている可能性が示唆されました。
香りと心理の関係をユーモラスに解明した研究です。
栄養学賞:「スムージーを飲む速度と幸福度の関係」
フランスの心理栄養学チームが、飲む速度と脳内ホルモンの変化を解析。
ゆっくり飲む人ほど“セロトニンの分泌が増える”ことを発見し、
「幸せはスピードではなく味わうことから」と示しました。
物理学賞:「スマートフォンを落とす角度は“人間の癖”で決まる」
カナダの研究者たちが、500人のスマホ落下データをAI解析。
結果、利き手や持ち方によって落下時の回転角度と衝突面が予測可能であることを確認。
実用性はともかく、“落とすのも科学”としてSNSで話題に。
心理学賞:「犬は飼い主のファッションによって性格が変わる?」
オーストラリアの動物心理学者が、飼い主の服装が犬の行動に与える影響を調査。
結果、スーツを着た飼い主の指示には従順になり、
カジュアルな服装ではリラックスした行動を取る傾向が確認されました。
工学賞:「椅子の“座りすぎ”が生む最適姿勢をAIが提案」
韓国の研究チームが、AIを用いて人間の長時間座位姿勢を解析。
“前かがみ15度+足裏接地”が最も疲れにくい姿勢であることを発見。
「人類の腰を救う研究」としてメディアでも注目されました。
地球科学賞:「火山灰の粒を楽器に使う実験」
アイスランドの地球物理チームが、火山灰を使って“音を出す”実験を実施。
結果、灰の粒径によって音色が異なり、**「地球が奏でる音」**として演奏会まで開催されました。
平和賞:「鳩が信号機を理解できるか?」
インドの研究者が都市部の鳩の行動を観察。
赤信号では止まり、青信号で飛び立つ傾向があることを発見。
「交通ルールを学ぶ鳩」としてSNSでバズり、教育的にも注目を集めました。
経済学賞:「会議の“うなずき回数”が成果を左右する」
スウェーデンの社会学チームが、オンライン会議中のうなずき頻度と意思決定スピードを解析。
結果、うなずきの多いグループほど意思決定が早く、満足度も高い傾向を確認。
ビジネス心理の観点から世界中の企業で話題に。
2025年の傾向は、「生活の中に科学を見つける」アプローチ。
身近なテーマを通じて、科学が日常と地続きであることを再確認させてくれる内容でした。
2024 vs 2025 を比べてみる視点
イグノーベル賞の面白さは、毎年テーマや研究傾向が微妙に変わるところにもあります。
ここでは2024年と2025年の受賞内容を比較しながら、科学トレンドの変化を整理してみましょう。
テーマ傾向の違い
2024年は「人間と自然の関わり」を中心に、
植物や動物、心理現象などの“観察型研究”が多く見られました。
一方、2025年はより“日常生活に根ざした実験”が増加。
スマートフォン、フライパン、椅子など、
私たちが毎日使うものを科学的に分析する傾向が強まりました。
これにより、イグノーベル賞は単なるユーモア科学から、
「生活科学」や「社会科学」への橋渡し的存在へ進化していることがわかります。
研究の多様性と国際化
両年ともに、ヨーロッパ・アジア・南米など多地域の研究が受賞。
特に2024年は日本・ベトナムの合同研究(カエルの鳴き声の研究)、
2025年は日本・ハンガリーの共同研究(ゼブラ牛実験)が注目を集めました。
これにより、イグノーベル賞はますますグローバルな科学イベントとしての地位を確立。
「笑い」という普遍的な感情が、国境を越えて研究者をつなげていることがわかります。
研究スタイルの変化
近年の傾向として、AIやデータ分析を取り入れる研究が急増。
2025年の「椅子姿勢AI」や「スマホ落下解析」などはその代表例です。
以前のように“奇抜な実験”が中心だった時代から、
今では**「テクノロジーで笑わせる科学」**へと進化しています。
注目ポイント:社会的意義の拡大
2024年・2025年に共通しているのは、
“笑えるけど実は役に立つ”という研究が増えている点です。
トイレットペーパーの効率化や牛の虫よけ実験など、
現実社会に応用できるテーマが多く見られました。
つまり、イグノーベル賞は「ムダを笑う賞」から
“ムダの中に価値を見出す賞”へ進化しているといえます。
なぜこの研究が選ばれたのか?共通点と評価軸
イグノーベル賞は、「おもしろい研究なら何でもOK」というわけではありません。
実はそこには明確な“哲学”と“評価軸”が存在します。
受賞した研究を分析すると、いくつかの共通点が見えてきます。
「笑い」と「考えさせる」の両立
創設者マーク・エイブラハムズ氏の理念である
「人々を笑わせ、そして考えさせる(Make people laugh, then think)」
これはイグノーベル賞の唯一絶対の審査基準です。
たとえば、
- 牛にゼブラ模様を描いた研究は「バカバカしいけど論理的」
- スリッパの飛ぶ角度研究は「くだらないけど再現性がある」
どちらも、笑いの奥に科学的ロジックがある点で評価されました。
笑いを“きっかけ”に、科学の本質を伝える――そこにこの賞の意義があります。
「身近な疑問」を科学的に証明している
イグノーベル賞の研究は、専門家だけでなく一般人にも“わかる”テーマが多いです。
つまり、**「自分の生活の中にある疑問を科学に変える」**という姿勢が重視されています。
例として、
- 2024年の「トイレットペーパー引き方最適化」
- 2025年の「スマホ落下角度」
どちらも日常生活の中の“ちょっとした出来事”を題材にしています。
笑いながら「たしかに気になる…!」と共感できるのが、この賞の魅力です。
「科学の敷居を下げる」社会的価値
イグノーベル賞は単なるエンタメではなく、科学教育やコミュニケーションの入口にもなっています。
授賞式のパフォーマンスや、受賞研究のユーモラスな発表方法は、
「科学を知らない人にも、科学を好きになってもらう」ための工夫なのです。
近年は教育現場での教材にも取り入れられるなど、
イグノーベル賞は“笑いで科学を広める装置”として進化しています。
「国際的・文化的多様性」も重視
もう一つ見逃せないのが、世界中から選ばれる多様な文化背景です。
2024・2025年ともに、アジア・欧州・南米など多地域から受賞者が出ており、
科学の普遍性と文化の多様性が共存しています。
「どんな国の人でも、ユーモアの中に真理を見いだせる」――
それが、イグノーベル賞の魅力であり、国際的な影響力の理由です。
このように、イグノーベル賞は“おもしろい研究”というより、
**「人間の好奇心を称える賞」**といったほうが正確です。
まとめ 〜最新イグノーベル賞から見えること〜
イグノーベル賞の世界は、毎年「人間の好奇心って本当にすごい」と思わせてくれます。
2024年・2025年の受賞研究を振り返ると、そこには3つのキーワードが見えてきます。
科学は“日常”の中にある
スマホ、椅子、トイレ、牛、植物――。
最新のイグノーベル賞に登場するテーマは、どれも私たちの身の回りにあるものばかりです。
つまり、“研究”とは特別なものではなく、日々の「なぜ?」を突き詰める行為だということ。
研究者たちは、誰も気に留めない疑問に真剣に向き合い、
そこから世界を笑顔にする発見を生み出しています。
「ムダ」と「ユーモア」が科学を前進させる
イグノーベル賞は、ムダを笑うための賞ではありません。
むしろ、「ムダの中にこそ発想がある」と教えてくれます。
ゼブラ牛のように実用化された例もあれば、
トイレットペーパーの研究のように“日常の改善”につながる研究もある。
笑いながら学ぶことが、結果的に社会の知を豊かにしているのです。
科学は人をつなぐ“共通言語”
イグノーベル賞は、科学を“笑い”という共通言語で世界に広めました。
どの国の人も、笑うことで考え、考えることで学ぶ。
その循環が、国境も文化も超えて共有されている――それこそがこの賞の最大の価値です。
🪶まとめの言葉
「人々を笑わせ、そして考えさせる(Make people laugh, then think)」
この理念が、2025年の今もまったく色あせていません。
イグノーベル賞は、科学に“心”と“遊び心”を取り戻すイベントであり続けています。
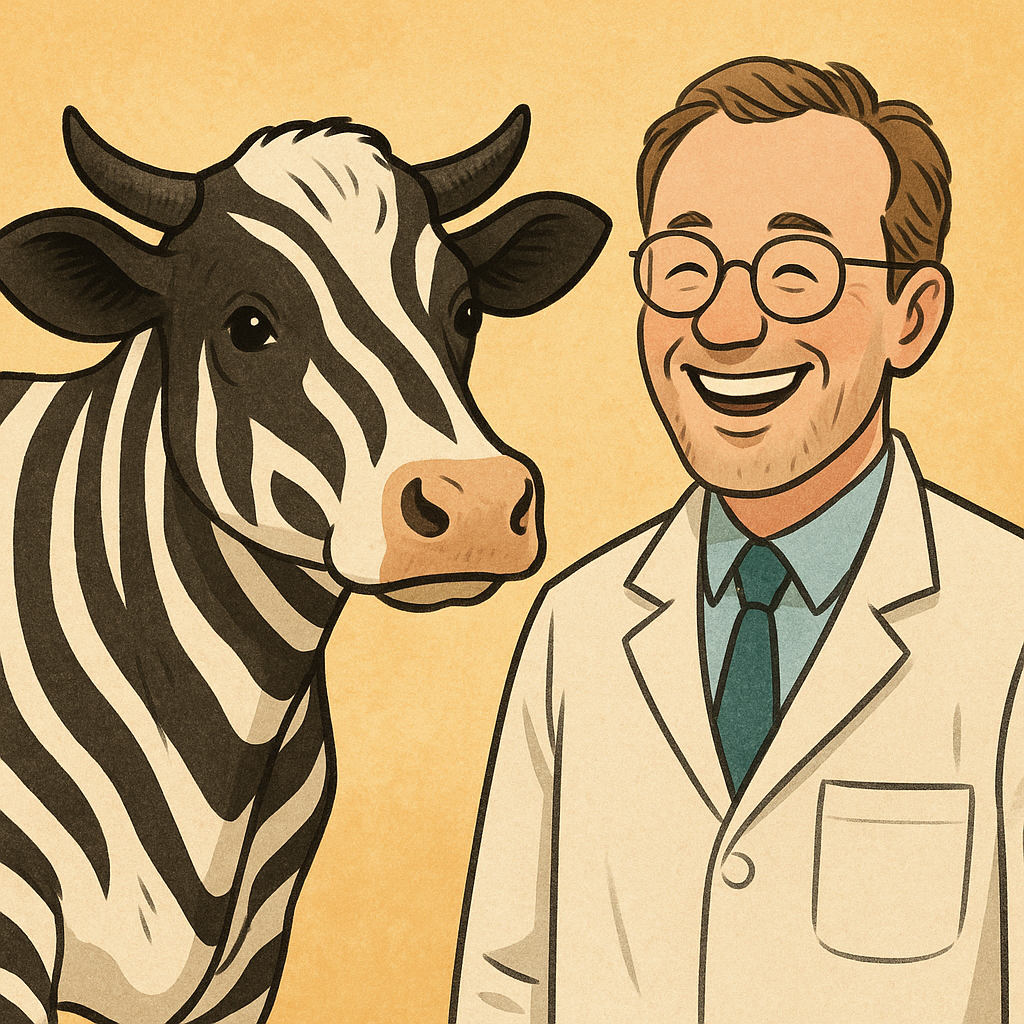
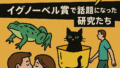
コメント